当たり前のことを当たり前に
五月の中ほど、教育委員5名で、秋田県と宮城県の視察研修をしてきました。何が目的かといいますと、一つは「全国学テで三年連続素晴らしい成績をあげている秋田県での取り組みを学び、中標津町の子ども達の学力向上に資するヒントを得たい」ということでした。もう一つは、施設一体型小中一貫教育の取り組みと課題を知りたい」ためでした。
視察結果の報告は、後日改めてしたいと思っています。
視察結果の報告は、後日改めてしたいと思っています。
ここでは、とても印象的なことを少しだけお話したいと思います。秋田県秋田市の訪問では、駅からも近く、市の中心地にある小学校1校と中学校1校で学校の様子授業の様子を見せていただき、校長先生との意見交換を行いました。また、秋田市教育委員会では、指導主事から秋田市の教育の状況を説明していただき、意見交換をしました。
この三ヶ所の訪問で、共通して聞かされた言葉が「私たちは特別なことはしていません。当たり前のことを当たり前にしているだけです」でした。私は、既に秋田県の教育に関する文章をさまざまに読んでいましたので、この言葉は知っていました。しかし、実際に訪問した三ヶ所で次々と聞かされると、やはり「う~~ん」と唸ってしまいました。私は心の中で「そんなことは分かっているんだよ。でも、その当たり前のことがなかなかできないんだよ」とつぶやいていました。
「子どもが家庭学習をするのは当たり前です」「朝ごはんは、ほとんど百パーセント食べてきています」という言葉もありました。また、タクシーの運転手さんに、秋田県の学力は高いですね」と話を向けると、「いやあ、一部ですよ。そんなでもないです」という返答でした。この運転手さんに「学校に、教育に、どんなことを望みますか」と訊いたところ、彼は「やっぱり、不登校なんかがないような……」というお話でした。
この三ヶ所の訪問で、共通して聞かされた言葉が「私たちは特別なことはしていません。当たり前のことを当たり前にしているだけです」でした。私は、既に秋田県の教育に関する文章をさまざまに読んでいましたので、この言葉は知っていました。しかし、実際に訪問した三ヶ所で次々と聞かされると、やはり「う~~ん」と唸ってしまいました。私は心の中で「そんなことは分かっているんだよ。でも、その当たり前のことがなかなかできないんだよ」とつぶやいていました。
「子どもが家庭学習をするのは当たり前です」「朝ごはんは、ほとんど百パーセント食べてきています」という言葉もありました。また、タクシーの運転手さんに、秋田県の学力は高いですね」と話を向けると、「いやあ、一部ですよ。そんなでもないです」という返答でした。この運転手さんに「学校に、教育に、どんなことを望みますか」と訊いたところ、彼は「やっぱり、不登校なんかがないような……」というお話でした。
秋田県は子どもの学力も高いのですが、自殺をする人の数も全国トップレベルということも聞いていましたので、教育委員会での意見交換の折、近野委員長がそれについて質問したところ、「やはり経済の状態が良くないですから……」との答えが返ってきました。経済の状態が良くなく、不登校もあり、生徒が荒れている学校もある……、では何が違うのか。私の頭の中に浮かんで消えたのは「伝統?文化?」という言葉でした。
視察研修から戻り、六月の初め3日間を使い六ヶ所で「中標津町の教育を考える教育懇談会」を開催しました。さまざまなご意見やご質問をいただき、大変勉強になったのですが、初めての経験の私にとって一番印象的だったのが、参加者の少なさでした。どの会場でも、学校関係者が圧倒的に多く、保護者や地域の方々は数人でした。
さて、このような二つの経験の中で、私の頭の中を少し整理してみました。これは、まだどなたにも話してはいません。教育委員会の内部に持ち出してもいませんし、教育委員の方々にも話してはいないのですが、私の頭の中を少し覗いてください。
さて、このような二つの経験の中で、私の頭の中を少し整理してみました。これは、まだどなたにも話してはいません。教育委員会の内部に持ち出してもいませんし、教育委員の方々にも話してはいないのですが、私の頭の中を少し覗いてください。

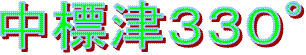
―子ども達に燦燦と太陽がふりそそぎ マル―
学習環境・学習習慣の整備充実
学力の向上・体力の向上
読書への親しみ
幼小中高の連携
地域の総合力による支え
ひ と: も の: しくみ:
例?:
「1年間に読書33冊でマル」
「家庭学習330日でマル」
そろそろ、教育を私たちの手に取り戻してもいいのではないでしょうか。東京で求められる施策が、そのまま中標津に必要とは限りません。
私の頭の中は、非常に漠然としたものです。キャッチコピー、キャッチフレーズの段階です。もう少し整理し、どなたかと議論の必要性があるようです。
学習環境・学習習慣の整備充実
学力の向上・体力の向上
読書への親しみ
幼小中高の連携
地域の総合力による支え
ひ と: も の: しくみ:
例?:
「1年間に読書33冊でマル」
「家庭学習330日でマル」
そろそろ、教育を私たちの手に取り戻してもいいのではないでしょうか。東京で求められる施策が、そのまま中標津に必要とは限りません。
私の頭の中は、非常に漠然としたものです。キャッチコピー、キャッチフレーズの段階です。もう少し整理し、どなたかと議論の必要性があるようです。
平成22年6月 教育長
小 谷 木 透
小 谷 木 透
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津町 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
中標津町 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333